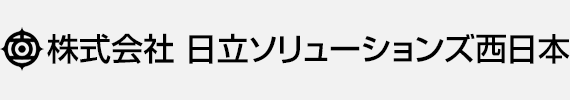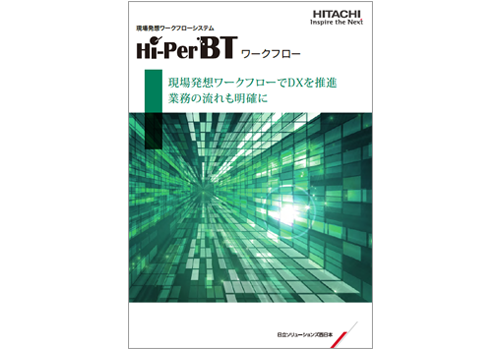- サイトトップ
- Hi-PerBT ワークフロー
- ワークフローコラム
- ワークフローシステムと基幹システムの連携
ワークフローシステムの連携|APIによる基幹システムとの連携例
ワークフローシステムと基幹システムを連携させることに焦点を当てつつ、
「ワークフローシステムの連携」に関する内容を紹介します。
-
ワークフローシステムと基幹システムの
連携はなぜ必要か? -
ワークフローシステムと連携できる
基幹システムの例 -
ワークフローシステムとグループウェアの
API連携も必要 -
ワークフローシステムと基幹システムを
API連携させる際のポイント -
『Hi-PerBT ワークフロー』で
申請・承認業務を効率化 - まとめ
ワークフローシステムとは、業務プロセスにおける一連の作業や手続きを自動化・可視化するためのシステムです。システムを導入すると業務全体の効率化がはかれるため、現場レベルだけでなく、経営視点でも大きな効果が見込めます。
特に承認を必要とする業務プロセスにおいては、企業内の重要な業務として認識されている基幹業務も関わってくるため、導入前と比較するとかなりの手間と時間を削減できるでしょう。また、基幹業務が関わってくると必然的にワークフローシステムと基幹システムの連携は欠かせません。
本記事では、ワークフローシステムと基幹システムを連携させることに焦点を当てつつ、「ワークフローシステムの連携」に関する内容を解説します。
ワークフローシステムと基幹システムの
連携はなぜ必要か?
基幹システム(ERPや会計、販売などの主要業務システム)は企業の中枢を担っているため、ワークフローシステムと連携すれば、データの自動転送やプロセスの自動化が実現します。ワークフローシステムの真価は基幹システムなどの主要システムとの連携で発揮されるため、業務効率を向上させるためにも連携は必須といえます。
たとえば、経費申請のワークフローで承認が完了すると自動的に会計システムに仕訳データが登録されるようにすれば、経理部門の手入力作業が不要となり、ミスが防げます。連携がない場合、承認後に別途手作業で会計システムへ入力する必要があり、業務負荷・入力ミス・処理の遅延といったリスクが発生するでしょう。
このように、ワークフローと基幹システムが連携すると部門間の業務がスムーズに繋がり、生産性向上と正確なデータ管理が実現します。
ワークフローシステムとAPI連携できる基幹システムの例
ワークフローシステムと連携できる基幹システムは、主に以下の8種類があります。
| 連携できるシステム | 連携による効果 |
|---|---|
| 会計システム | 経費申請や支払依頼の承認データを自動仕訳化し、会計入力の手間やミスを削減 |
| 勤怠管理システム | 勤怠申請や残業申請がそのまま勤怠システムに反映され、勤務実績の正確な集計が可能 |
| 経費計算システム | 申請内容と領収書を一元管理し、精算の承認から支払までのフローを効率化 |
| 電子契約システム | 契約書の承認と電子署名を一体化させ、契約業務のスピードアップとコンプライアンス強化 |
| 電子帳簿システム | 承認済みの帳票データが自動保存され、電子帳簿保存法への対応が容易に |
| 人事システム | 異動・採用などの申請フローと人事データの更新を連動させ、手続きミスの防止と迅速化 |
| 販売管理システム | 見積・受注・請求関連の承認処理と販売データの連携により、営業プロセスを円滑化 |
| 在庫管理システム | 発注申請と在庫の更新処理を自動連携し、欠品や過剰在庫のリスクを低減 |
ワークフローシステムは、会計・人事・販売などの基幹システムと連携ができ、申請・承認データをリアルタイムで各業務に反映できるようになります。結果、二重入力の回避や処理スピードの向上、データ整合性の担保といった効果が得られます。
すべてのシステムといきなり連携をはかるのはハードルが高いため、連携するシステムには優先順位をつけましょう。連携の優先順位は、業務のボリュームや申請頻度の高い領域(会計や経費、人事など)を中心に検討すると効率的です。自社の業務特性に応じて段階的に拡張していけば、業務全体の最適化がはかれるでしょう。
会計システム
会計システムとは、企業の財務情報を管理し、仕訳や決算処理、帳簿の作成などを自動化・効率化するための基幹システムです。
ワークフローシステムと会計システムを連携すれば、経費申請や支払い処理の承認情報がそのまま仕訳データとして会計システムに自動連携されます。経理部門の手動入力作業が大幅に削減され、入力ミスのリスクが低下するでしょう。
たとえば、従業員が出張時の精算申請を行った際、ワークフロー上で承認されたデータが自動で会計システムに登録されるため、経理担当者は内容確認のみで済みます。経理部門全体の業務負荷が軽減されるだけでなく、月次決算や監査対応の効率も向上するでしょう。
勤怠管理システム
勤怠管理システムとは、従業員の出退勤や休憩・残業などの勤務状況を記録・管理するシステムです。
ワークフローシステムと勤怠管理システムの連携によって、残業・休暇申請といった申請内容がリアルタイムで勤怠データに反映が可能です。手入力の手間がなくなり、勤怠情報の整合性と集計精度が高まるでしょう。
たとえば、従業員が有給休暇を申請し、上長が承認した時点で、その情報が自動で勤怠システムに登録されます。人事部門における管理工数の削減だけでなく、従業員の申請状況の確認もスムーズになります。
経費計算システム
経費計算システムとは、業務で発生した交通費や宿泊費、接待費などの経費を申請・承認・精算するプロセスを一元化するシステムです。領収書の添付や経費ルールの自動チェック機能が備わっており、経理業務の効率化に寄与します。
ワークフローシステムとの連携によって、交通費や備品購入などの経費申請が一連のフローで完結が可能です。領収書の添付から承認、精算までを一元管理でき、業務全体の透明性と効率が向上します。
たとえば、営業担当者が出張費用を申請し、部門長と経理部門の承認を経た情報がそのまま経費精算システムに送られて、二重確認や再入力の手間を削減し、全社的に精算業務の時間短縮が実現します。
電子契約システム
電子契約システムとは、契約書の作成や署名、保管をすべてオンライン上で完結できるようになるシステムです。印刷や郵送を省き、タイムスタンプや電子署名により法的効力を確保しつつ、契約業務をスピーディに進められます。
ワークフローシステムと連携すれば、契約書の承認と締結処理を1つのフロー内で完結させられます。契約書の作成から承認、署名までをデジタル上で行えるため、契約締結までのスピードが格段に上がるでしょう。
たとえば、購買部門が取引先との契約書を起案し、社内承認を得た後にそのまま電子契約に移行すれば、印刷と郵送の手間を省き、テレワーク中でも対応ができるようになります。
電子帳簿システム
電子帳簿システムとは、帳簿書類を電子的に保存・管理するためのシステムです。主に電子帳簿保存法に準拠する形で運用されます。
ワークフローシステムとの連携によって、承認済みの申請書や帳票を電子保存し、法定要件を満たす形での管理ができるようになります。特に電子帳簿保存法への対応に有効です。
たとえば、経費精算や稟議書などが承認されたタイミングで、自動的に電子帳簿システムに保存されるようにすれば、業務の流れを妨げることなく法令遵守が可能になります。導入によって経理・総務部門におけるペーパーレス化が進み、保管コスト削減にも繋がるでしょう。
人事システム
人事システムとは、従業員のプロフィールや勤続年数、給与情報、評価履歴などを管理し、人材の配置や育成、評価などの人事戦略を支援するシステムです。組織改編や人事異動のスムーズな処理にも活用されます。
ワークフローシステムとの連携によって、入社・異動・退職といった人事イベントの申請から人事データの更新までを一貫して行えます。これにより、入力ミスや申請漏れのリスクを減らし、管理効率が向上します。
たとえば、社員の異動申請が承認された際、その情報が自動で人事システムに反映されるようにすれば、人事部の手作業を減らし、正確な人員管理が可能になります。従業員が多い、中規模以上の企業で特に効果を発揮するでしょう。
販売管理システム
販売管理システムとは、商品の見積りや受注、出荷、請求、入金までの一連の販売プロセスを管理するシステムです。販売状況の可視化や在庫管理との連携、請求漏れの防止など、営業部門と経理部門をつなぐ役割も担います。
ワークフローシステムと連携すれば、見積や受注、請求に関わる承認プロセスを迅速化し、営業活動のスピードを高められます。たとえば、見積書を作成した営業担当者がワークフローを通じて上長に承認を依頼し、承認完了後に販売管理システムにデータが登録されるといったフローによって、業務がシームレスに進行するでしょう。
営業部門では、見積承認の遅れが商談機会の損失に繋がることも珍しくないため、導入は成約率の向上にも貢献する期待が持てます。
在庫管理システム
在庫管理システムとは、商品の入出庫や棚卸、在庫移動などの情報をリアルタイムで管理するシステムです。在庫の過不足や滞留の可視化によって、適正在庫を維持し、業務コストや機会損失の抑制に役立ちます。
ワークフローシステムとの連携によって、発注申請や棚卸報告などの情報を自動で在庫データに反映が可能です。これにより、在庫数の正確性が向上し、欠品や過剰在庫のリスクを低減できるでしょう。
たとえば、発注申請が承認された段階で、在庫管理システムに自動的に反映される仕組みを整備すれば、購買・物流部門の調整作業がスムーズになります。製造業や小売業など在庫の流動性が高い業界には特に有効な連携といえます。
ワークフローシステムとグループウェアのAPI連携も必要
グループウェアとは、社内の情報共有やコミュニケーション、スケジュール管理などを目的とした統合型ツールです。代表的な機能に、掲示板やカレンダー、ファイル共有、メールなどがあり、組織内の情報伝達や業務調整を効率化します。
グループウェアにワークフロー機能を備えている製品もありますが、本来のワークフローシステムとは目的や機能が異なります。グループウェアのワークフロー機能は簡易的な承認処理にとどまることが多く、業務プロセスの最適化や基幹システムとの高度な連携を前提とした本格的な機能には対応していません。
そのため、グループウェアとワークフローシステムは役割が異なり、両者を連携させることが情報の一元化と業務効率の最大化へと繋がります。
たとえば、スケジュール管理と承認業務を連動させることで、申請・承認のタイミングを各担当者が見逃さずに済むため、組織全体のフローをスムーズに進められます。
ワークフローシステムと基幹システムをAPI連携させる際のポイント
ワークフローシステムと基幹システムを連携させる際のポイントは以下のとおりです。
- 自社で運用する基幹システムとの連携が可能か
- オンプレミスやクラウドなど導入形態を選べるか
- 社内だけで連携から運用保守まで可能かどうか
ワークフローシステムと基幹システムを連携させる際、自社がすでに運用している基幹システムとスムーズに連携できるかどうかは、選定時の前提条件となります。次に、システムの導入形態としてオンプレミスやクラウドなど、業務環境に合った選択肢が用意されているかも重要です。
また、システム連携後の運用・保守を社内で対応可能かどうかも確認しておきましょう。これらを踏まえたうえで選定すれば、連携後の運用トラブルやコスト増を回避できます。
自社で運用する基幹システムとの連携が可能か
自社ですでに運用している基幹システムとワークフローシステムが連携可能かどうかは、スムーズな業務フローを構築する上で非常に重要なポイントです。連携ができない場合、手動でのデータ転記や二重入力が発生し、業務の効率化どころか負荷が増して本末転倒な事態にもなりかねません。
たとえば、会計システムと連携ができないと、経費精算データを毎回経理部門が手入力しなければならず、ミスや遅延が頻発する要因となります。このような連携不全は、業務全体の生産性低下や従業員の不満要因にも繋がりかねません。
そのため、導入時は既存の基幹システムと連携ができるか必ず確認してから導入を検討しましょう。

オンプレミスやクラウドなど導入形態を選べるか
導入形態の柔軟性も、システム選定における大きな判断材料です。オンプレミス型とクラウド型では運用コストやセキュリティ要件が異なるため、自社のIT方針や運用体制に合った選択ができるかは重要です。
- オンプレミス型とは:サーバーやシステムを自社内に設置・運用する方式
- クラウド型とは:インターネット経由で外部のクラウドサービスを利用する方式
セキュリティ要件が厳しくクラウド利用が制限されている企業が、クラウド専用のワークフローシステムを選んでしまうと、運用に支障をきたします。逆にクラウド環境を前提とする企業がオンプレミス型を選んでしまうと、保守管理の負担が増えて運用が大変になります。
双方の導入形態に対応しており、自由に選べるシステムであればその心配が不要であるため、導入時の失敗リスクを軽減できるでしょう。
社内だけで連携から運用保守まで可能かどうか
ワークフローシステムと基幹システムの連携は導入後も継続的な保守や調整が必要です。そのため、連携から運用保守までを自社内で対応可能かどうかは重要なポイントになります。外部に依存しすぎると、対応の遅れやコストの増大に直結するため、長期的な目線で考えても社内完結できるかは重要です。
たとえば、設定変更や不具合対応のたびにベンダーに依頼が必要な場合、対応に時間がかかり、業務が停滞する可能性があるでしょう。社内で最低限の連携・保守をできる体制があれば、運用の安定性が高まり、柔軟なシステム運用が実現します。
『Hi-PerBT ワークフロー』で申請・承認業務を効率化
これからワークフローシステムを導入しようとしている人には、『Hi-PerBT ワークフロー』がおすすめです。基幹システムとの柔軟な連携が可能なだけでなく、オンプレミス・クラウドの両形態にも対応しています。さらに社内での運用保守を想定した設計と、選定時の重要ポイントをすべて網羅しているため、本記事で紹介した選定ポイントを満たしています。
業務に応じて段階的な拡張も可能で、企業の成長に応じた柔軟な対応も実現。無料で利用できるオンライン試用環境も用意されているため、導入前に自社業務との適合性の確認も可能です。
導入を失敗するリスクの低いシステムであるため、ワークフローシステムの知識が少なくて悩んでいる方には特におすすめできるシステムといえるでしょう。
まとめ
ワークフローシステムと基幹システムの連携は、業務効率と正確性を高めるために不可欠です。基幹業務などの主要業務データを自動連携すれば、二重入力の削減や処理の迅速化、情報の一元管理が実現します。また、グループウェアとの連携により情報共有も強化され、業務全体の最適化がはかれるでしょう。
導入するシステムを選定する際は、自社の運用環境に適したものを選ぶことが大切です。特に連携性は既存のシステムを活かせるかどうかを左右するため、確実に連携できるシステムを選ばなければいけません。