- サイトトップ
- 販売管理・生産管理システム Hi-PerBT KIT3
- 販売管理コラム
- ERPパッケージとは?種類や特徴、導入のメリット・デメリットをわかりやすく解説
ERPパッケージとは?種類や特徴、
導入のメリット・デメリットをわかりやすく解説
ERPの開発をする方向けに、ERPパッケージの基本的な情報やメリットを解説します。
最後にはスクラッチ型とパッケージ型でどちらがおすすめかも取り上げるので、参考にしてみてください。
ERPパッケージは、企業が持つ基幹業務に関するデータを効率良く管理するためのソフトウェアパッケージです。ERP(システム)を導入する際に用いることが多く、自社の業務形態に合わせて最適なパッケージを選択できれば、効率的なデータ管理や業務の自動化など、高い効果を発揮するでしょう。
そのためERPパッケージの詳細は、ERPを導入して、ゼロから自社にマッチしたシステムを構築したい企業が把握しておくべき内容であるといえます。
本記事では、ERPの導入を検討している方向けに、ERPパッケージの基本的な情報やメリットを解説します。後半では、導入するERPパッケージを選ぶポイントも解説しており、自社に最適なパッケージを選ぶ際の役に立つでしょう。
ERPパッケージとは?
ERPパッケージとは、ERPシステムを構築する機能などがパッケージ化されているソフトウェアパッケージです。企業の経営資源を効率よく管理するうえで必要な機能をパッケージ化した既製品となっており、利用することでERPをゼロから開発するよりも効率よく構築できます。
なお、ゼロから開発するものはスクラッチ型といって、自社で必要とする機能のすべてを網羅できるようなERPを構築することが可能です。ただし、ERPパッケージと比べるとかなりのコストがかかるため、企業独自の業務があるようなケースでない限りは適さないでしょう。
ERPとは
ERPとは、「Enterprise Resources Planning」の略称で、企業を構成する基本的な資源要素(「ヒト」「モノ」「お金」「情報」)を一か所に集約して、効率よく活用しようとする考えをさします。ERPは「考え方」としての用語ではありますが、最近では、その考え方を実現するための「システム」を意味する用語として使われることの方が多いです。
つまり、ERPは資源要素を一か所に集約して活用するためのシステムであるということになります。具体的には、給与管理(ヒト)や在庫管理(モノ)、経理管理(お金)、基幹業務に関わるデータ(情報)をシステム内ですべて管理できるイメージです。
ERPパッケージの種類
ERPパッケージには以下の4種類があります。
ERPパッケージの種類
- 統合型ERPパッケージ
- コンポーネント型ERPパッケージ
- 業務ソフト型ERPパッケージ
- ERPクラウドサービス
これらは大きく分けると、業務を幅広くカバーできるように機能を豊富に搭載しているものと、業種や業務に特化したものの2種類に分けられます。「どのパッケージなら優れている」といったようなことはないため、自社の用途に合わせて最適な種類を選ぶことが重要です。
統合型ERPパッケージ
統合型ERPパッケージは、会計・販売・人事・給与など、企業経営に必要なデータを一つに統合して管理できるパッケージです。他のERPパッケージだと、特定の業務に特化したものであったりしますが、統合型ならERPで必要となる業務の多くをカバーできるため、比較的導入しやすいでしょう。
逆に、特定の業種に特化したERPを構築したい場合には適していません。そのため、初めてERPの導入を試みる企業や汎用的なERPの導入を希望している企業におすすめのパッケージといえます。
【統合型ERPパッケージの導入がおすすめの企業】
- 比較的、汎用性のあるERPを導入したいと考えている企業
- システムによって効率化をはかる業務の範囲が広い企業
コンポーネント型ERPパッケージ
コンポーネント型ERPパッケージは、総務・会計・生産などの各業務から必要な業務システムを選択・組み合わせて導入するパッケージです。必要な機能をピックアップしてERPを構築するため、統合型と比べると組み込む機能が少なく、費用も抑えられます。
また、必要なシステムを選択することで効率化をはかる業務の範囲を狭められるため、スモールスタートでの導入を検討している企業に最適です。
【コンポーネント型ERPパッケージの導入がおすすめの企業】
- スモールスタートでの導入を検討している企業
- 特定の業務に特化したERPを構築したい企業
業務ソフト型ERPパッケージ
業務ソフト型ERPパッケージは、会計、人事・労務、生産管理など、特定の分野の業務に特化して一元管理を行うパッケージです。事業部門や業務単位で課題解決するタイプで、部門ごとの業務効率化がはかれます。たとえば、経理業務に特化したパッケージを導入すれば、給与管理や伝票作成、領収書の管理などの経理業務をカバーできるERPを構築可能です。
特定の業務に特化したパッケージであるため、適用範囲も狭くなってようとは限られますが、統合型ERPやコンポーネント型ERPよりも導入目的が明確になりやすいため、比較的導入しやすいでしょう。
【業務ソフト型ERPパッケージの導入がおすすめの企業】
- 効率化をはかりたい業務が絞られている企業
- 導入目的が明確になっている企業
ERPクラウドサービス
ERPクラウドサービスは、クラウド環境で利用できるERPです。パッケージ型とは少し異なり、すでにシステムとして用意されています。保守運用はベンダー任せで、メンテナンスも不要なため、専門知識のある人材がいなくても利用できるでしょう。

ただし、専門知識を持つ人材が不要な反面、カスタマイズ性は低くなり、自社の希望する細かな機能の追加などはできません。そのため、提供されているERPクラウドサービスを複数比較して、自社に導入する価値のあるものを探すという手間がかかります。
なお、他のパッケージと比べると導入コストは抑えられるため、導入しやすい点はERPクラウドサービスの強みです。
【ERPクラウドサービスの導入がおすすめの企業】
- すでに用意されているERPを導入したい企業
- コストをできる限り抑えてERPを導入したい企業
ERPパッケージの内容例
これまでのERPパッケージの種類を踏まえ、ERPを導入する際はパッケージ内容の吟味が必要です。パッケージ内容は提供する企業によって異なるため、その種類は多岐にわたります。そのため、パッケージ内容を吟味する際の参考として、パッケージの内容例を以下で紹介します。
-
ERPパッケージの内容例
- 大企業向けパッケージ
- 中小企業向けパッケージ
- 特定の業界向けパッケージ
必ずしも、大企業は大企業向けパッケージを、中小企業は中小企業向けパッケージを導入しなければいけないわけではありません。あくまでもパッケージの内容を吟味したうえで、導入するべきか検討する点は間違えないようにしましょう。
-
大企業向けパッケージ
大企業向けパッケージは、主に統合型ERPパッケージであるケースが多く、幅広い業務をカバーできる機能を含んでいます。たとえば、財務会計をはじめ、調達管理や統合業績管理などの管理系業務、そして製造などの業務システムにいたる、企業活動に関わる全ての情報を一元管理できる機能が搭載されています。カスタマイズ性にも優れており、その企業独自の業務に対しても柔軟に対応可能です。
大企業の場合、決められた独自の業務内容があるケースも多く、ツールを導入する際は業務に合わせなければいけないことも珍しくありません。そのため、大企業向けパッケージはカスタマイズしやすいことが前提に作られています。
-
中小企業向けパッケージ
中小企業向けパッケージは、コンポーネント型や業務ソフト型のパッケージが採用されています。そのため、中小企業向けパッケージには財務管理に特化したパッケージやリソース管理に特化したパッケージなど、特定の業務に特化したパッケージが組み込まれていることが多いです。
その理由は、導入コストにあります。大企業と比較すると中小企業の場合、高額なERPパッケージの導入はハードルが高く、導入に一歩踏み切れないケースも珍しくありません。このような点を踏まえ、中小企業向けパッケージは、コストを抑えるために最低限必要な機能だけを搭載して提供されているものが多いです。
-
特定の業界向けパッケージ
特定の業界向けパッケージは、その名のとおり業界を絞ったうえで必要な機能を搭載しているパッケージです。たとえば、「製造業向け」といったように漠然としたものではなく、自動車業界向け、産業用機械製造業界向け、といったように業界を絞ってパッケージ化されています。
その業界特有の業務内容に合わせた機能が搭載されており、機能は、業界ごとの管理方法や独自の決まりなどによって異なります。食品業界だと衛生面など、業界ならではの複雑な課題や規制があり、それに対応した機能が搭載されていたりします。
ERPパッケージを導入するメリット
ERPを構築する方法として、パッケージ型以外にもゼロからこだわって開発するスクラッチ型というものもあります。スクラッチ型は自社に合わせてゼロから作り上げるため最適なシステムが完成しますが、コストが高くなります。そのため、ERPパッケージを利用した方がコストも抑えられ、ERP構築の効率も良いでしょう。
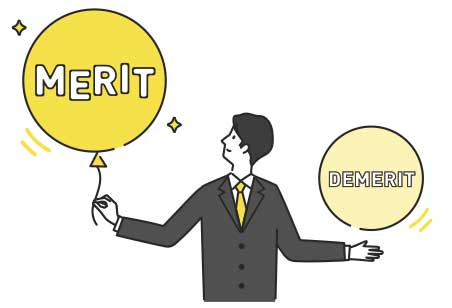
以上の点を踏まえ、ERPパッケージを導入することによって具体的にどのようなメリットがあるのかを解説します。メリットは以下のとおりです。
-
ERPパッケージを導入するメリット
- 一元管理による業務効率の向上
- 経営層の意思決定スピードの向上
- 業務の属人化の解消
- コストの削減
-
一元管理による業務効率の向上
ERPパッケージには複数の業務に対応した機能が組み込まれているため、利用することによって対応した部門のデータを一元管理できます。統合型のパッケージなら、企業全体の業務を一元管理することもできるでしょう。
また、一元管理によって、各部門の連携を強化することも可能です。たとえば、システム内に入力するデータで生産管理部門と工程管理部門で同じ内容のものがあったとします。この場合、担当者が一度入力するだけで、双方の部門で内容を確認できるため、情報共有のスピードが向上し、連携の強化によって業務が効率化するでしょう。
-
経営層の意思決定スピードの向上
ERPパッケージは前項で触れたように、データの一元管理ができます。これにより、経営層が必要とするデータも一元管理できるため、システムの利用によって素早く必要な情報を知ることが可能です。経営層の意思決定に必要な情報をシステムから素早く抽出できれば、結果的に意思決定スピードは向上します。
また、パッケージに含まれる機能の中には、現在の経営状況の可視化や分析ができる機能もあったりします。たとえば、過去の売上データを一つの表にまとめて、経営状況の素早い理解を促す機能や、現在の状況を踏まえた将来の需要予測ができる機能などです。これらの機能を利用することで経営方針の策定などの意思決定はさらに効率的になるでしょう。
-
業務の属人化の解消
ERPパッケージはすでに必要な機能が組み込まれているため、独自にカスタマイズを繰り返す必要がありません。そのため、システムの利用方法を覚えてしまえば誰でも利用できるため、属人化の解消・防止に役立つでしょう。仮に、利用者が一人しかいなかったとしても、ERPパッケージの提供元に問い合わせれば利用方法を教えてもらうことも可能です。
また、ERPパッケージには効率化の機能だけでなく「権限の移譲機能」や「代理処理機能」なども含まれているため、他の担当者に使用の権限を譲渡したりできます。たとえば、普段からシステムを利用している担当者が病気などの利用で長期休暇に入ってしまったとしても、権限を譲渡すれば引き続き別の担当者がシステムを運用可能です。
-
コストの削減
ERPパッケージでは、業務プロセスの自動化によるコストの削減が可能です。たとえば、人の手によって入力や計算していたものを、バーコード読み取り機能や自動計算機能で置き換えることによって自動化がはかれます。これにより、自動化する業務を担当していた人の負担を削減でき、労働時間の短縮などに期待できるでしょう。
労働時間が短縮すれば、人件費や運営コストの削減が可能です。また、自動化によって浮いた時間を他の業務に使うなどして、うまく活用できれば生産性の向上もはかれます。
ERPパッケージの導入によって、パッケージ内に含まれる機能に対応した業務の効率化がはかれます。また、パッケージ化した内容によっては、複数の部門同士の連携を効率化するものもあるため、情報共有が迅速化して経営層の意思決定スピードが向上します。
ERPパッケージを導入するデメリット
ERPパッケージには導入するメリットがある一方で、デメリットもあります。デメリットを知ることは、ERPパッケージを導入する価値をより深く理解することにもなるでしょう。デメリットは以下のとおりです。
-
ERPパッケージを導入するデメリット
- 導入コストがかかる
- 企業の業務内容が独自のものだと適用しない可能性がある
-
導入コストがかかる
ERPパッケージにかかるコストはピンからキリまでさまざまですが、コストを抑えようとすればするほど、搭載されている機能が減ってしまう可能性が高いです。特に統合型のパッケージは幅広く業務に対応できるように機能を豊富に搭載しているため、かかるコストが大きくなりやすいでしょう。
仮に予算がそこまで確保できない場合は、あえて利用する機能を絞ってシステムを構築するのも一つの方法です。場合によっては業務に特化している必要な機能だけを組み込んだタイプのパッケージもあるため、そのようなパッケージを選択すればコストを抑えられるでしょう。
-
企業の業務内容が独自のものだと適用しない可能性がある
ERPパッケージは過去の導入実績の内容を参考に作られているものが多いため、汎用性が高い仕様になっているものが多いです。そのため、企業独自の業務がある場合には、パッケージを導入してもその業務に対応できない可能性があります。
独自の業務に対応したERPを構築したいのであれば、スクラッチ型の導入を検討しましょう。スクラッチ型ならゼロからシステムを構築するため、自社の独自の業務にも柔軟に対応できるシステムが作れます。
ただし、スクラッチ型にすると導入コストが大きくなりやすいため、それなりの予算を確保しておかなければいけません。ものによっては数千万円、数億円とかかることも考えられます。
比較的コストを抑えられるタイプのERPパッケージもありますが、基本的にどのパッケージを導入するにしてもコストがかかります。企業が持つ予算によっては、導入を再検討せざるを得ない可能性もあるでしょう。
また、パッケージ化されているものは、基本的に汎用性の高い機能が組み込まれているため、企業独自の業務に対しては適応しない可能性があります。独自の業務に対応させるためには、スクラッチ型の導入を検討する必要があるでしょう。
導入するERPパッケージを選ぶ際のポイント
ERPパッケージは種類ごとに搭載されている機能や価格が異なるため、導入するパッケージを選ぶ際は自社にマッチしたものを選ばなければいけません。自社にマッチしたERPパッケージを導入するためには、以下4つのポイントを意識して選びましょう。

-
導入するERPパッケージを選ぶ際のポイント
- 自社の規模や業界に合ったものか
- 他システムとの連携性は問題ないか
- サポート体制は十分か
- 費用は問題ないか
-
自社の規模や業界に合ったものか
ERPパッケージは大きく分けると、幅広い業務をカバーできる統合型のようなパッケージと業界・業務に特化した機能が限られているパッケージの2種類に分けられます。どちらのタイプを導入するべきかは、自社の規模や業界に合わせて決めることが重要です。
たとえば、大企業のように部門がいくつもあり、各部門の連携強化やそれぞれの業務の効率化を目的とするなら、統合型のパッケージが最適です。一方で、自動車業界や医薬品業界など特定の業界に精通したパッケージを希望する場合には、統合型よりも業界・業務特化型のパッケージの方が適しています。
搭載されている機能に目を向けるのも大切で、自社で必要とする機能が搭載されていなければ、特化型のパッケージであっても導入価値は薄れてしまうでしょう。
-
他システムとの連携性は問題ないか
ERPパッケージは統合型のように幅広く業務をカバーできるものであっても、すべてを完全にカバーすることはできません。そのため、不足する機能を補うためにも他システムとの連携が取れるかどうかは重要なポイントです。
たとえば、経費管理ができる機能を搭載しているパッケージがあったとします。給与の管理はできるが、出退勤の詳細までは管理できない場合、出退勤を管理しているシステムとの連携が必要です。もし連携が取れなかった場合、逐一出退勤の詳細をERPに入力するなどの手間がかかるでしょう。
以上のように、連携が取れるだけでERPの活用効率はさらに向上するため、他システムとの連携性に問題ないかを確認しておくことは大切です。
-
サポート体制は十分か
ERPパッケージはシステムである以上、イレギュラーの操作や追加のカスタマイズなどが要因でエラーや障害が出ることもあります。そのような時に提供側のサポートが充実していなければ、エラーや障害を解決すること自体が難しくなってしまうでしょう。
エラーが発生した場合、ERPでカバーしている業務が基幹業務(企業経営の基盤となる業務)だと、場合によっては企業全体の業務が停止してしまうことも考えられます。もし業務停止などの事態になってしまえば、企業が受ける損失は計り知れないでしょう。
そのため、上記のようなリスクを最小限に抑えるためにもサポート体制が十分であるかどうかは、パッケージを選ぶ際によく確認しなければいけません。
-
費用は問題ないか
ERPパッケージは搭載している機能が多いほど費用が高くなるため、場合によっては予算をオーバーすることも考えられます。特にオンプレミス型のような自社ネットワークに組み込むタイプのシステムだと、導入コストはかなり高額になりやすいため注意しなければいけません。
ただし、コストを抑えたいからといって必要な機能を削るようなこともあってはいけません。そのため、自社が許容できる費用で収まっているかどうかと併せて、必要な機能が確保できているかの両方を踏まえてパッケージ選びをすることが重要です。
また、オンプレミス型とは異なりクラウド型のERPパッケージを導入する場合はランニングコストも想定しなければいけません。なぜなら、クラウド型の多くは月額料金制を採用しているものが多いためです。
どれかのポイントに絞って選ぶのではなく、ポイント全てを総合して選びましょう。
規模感に合っていなければ余計な機能が多い・不足しているなどの問題が発生しますし、他システムとの連携性に問題があれば既存システムを有効活用することもできません。また、サポート体制が充実していなければ、利用方法が分からなくなった際の対処法が限られてしまいます。
まとめ
ERPパッケージとは、ERPシステムを構築する機能がパッケージ化されているソフトウェアパッケージです。統合型や特化型などの種類があり、自社の業務を幅広くカバーできるものもあれば、一部の業務に特化したタイプのパッケージもあります。
どのようなパッケージを導入するべきかは、業種や規模感、コストなどによって異なります。搭載する機能が多ければその分コストが大きくなるため、場合によっては導入を再検討しなければいけない可能性も出てくるでしょう。また、パッケージによっては業務を100%カバーできないものもあるため、他システムとの連携が必要な場合もあります。
さまざまな種類のパッケージがあるため、自社に導入を検討している方は、まずは必要とする機能や予算をチェックし、どのようなパッケージが世の中には展開されているのかを知るところから始めましょう。

